こんにちは、ルトです。
新人の採用担当をしていると、就活生のみなさんからよくこんな声を聞きます。
- 「最終面接がめちゃくちゃ和やかで、雑談ばっかりだったんです!」
- 「趣味の話ばかりで、逆に拍子抜けしました」
- 「これって合格フラグですよね?」
たしかに、面接官が笑顔でフランクに話してくれると安心しますよね。緊張感から解放されて、「これはもう内定をもらったに違いない!」と感じるのも自然なことです。
でも、採用担当の立場からはっきり言います。
「雑談=合格」とは限らないんです。むしろ油断してしまうことで、最後の最後で評価を落とすケースも少なくありません。
この記事では、なぜ最終面接が雑談っぽくなるのか、学生が陥りやすい失敗ポイント、そして雑談面接を突破するための秘訣について、現場の視点でお話しします。
最終面接が雑談っぽくなる理由
最終面接は、企業にとって「この人を仲間として迎え入れて大丈夫か?」を確認する場です。
一次面接や二次面接では、スキルや志望動機、適性などをしっかりチェックしています。つまり最終まで残った時点で、基本的な能力や条件はクリアしていると見なされているんです。
では最後に何を見ているのか?
それは 人柄・価値観・相性 です。
だからこそ、堅苦しい質問ではなく、あえて「休日はどう過ごしてるの?」「最近ハマっていることは?」といった雑談風の質問が増えるんです。
表面的には雑談に見えても、実際には「一緒に働くイメージができるか」「自然体でも安心して任せられる人か」を確かめています。
「雑談=合格」と思い込むのは危険
採用担当の私からすると、ここで油断してしまう学生はとても多いです。
- 面接官がにこやかだった → 内定確定!
- 趣味の話で盛り上がった → 評価が高かったに違いない!
と、勝手にプラスに解釈してしまうんですね。
でも、和やかな雰囲気は「あなたを安心させるため」かもしれませんし、最後に素の姿をチェックするための仕掛けかもしれません。
つまり、雑談は試験の一部なんです。
学生が雑談面接で陥る失敗3選
1. 敬語が急に崩れる
和やかさに引きずられて「マジっすか!」や「やばいっすね!」など、普段の口調が出てしまうケース。
本人は「距離が縮まった」と感じても、採用担当からすると「社会人としてまだ不安」と映ります。
2. 話が浅すぎる
趣味や休日の過ごし方を聞かれて「特にないです」と答えてしまう学生も少なくありません。
本当は人となりを深掘りするチャンスなのに、これでは「受け身で主体性がない」とマイナス評価になってしまいます。
3. 聞かれたことだけで終わる
「趣味はランニングです」だけで会話を閉じてしまうのもNG。
雑談の中でも「そこからどう話を広げるか」「自分の軸とつなげて語れるか」が見られています。
雑談だからこそ「どう話すか」が大事
最終面接で問われているのは、話の内容そのものよりも「どう話すか」です。
- 相手に伝わりやすい言葉を選べるか
- 自然体で誠実な態度を保てるか
- 相手の話に興味を持って広げられるか
こうした姿勢が、雑談のやり取りの中で浮き彫りになります。
雑談面接を突破する3つのコツ
1. 普段の言葉遣いを意識して練習する
ゼミや友達との会話ではカジュアルでも構いませんが、面接では「丁寧な日常会話」ができるかが大事。練習のときから意識しておくと、和やかな雰囲気でも崩れません。
2. 趣味や日常のエピソードをストックしておく
「特にないです」で終わらないように、自分の趣味や最近の取り組みを3つほど用意しておきましょう。
たとえば「ランニング→大会に挑戦して継続力を培った」など、自己PRにつながる形にすると強いです。
3. 話を広げる姿勢を見せる
面接官が「映画が好きなんだね」と言ったら、「実はその経験から観察力が鍛えられて…」と広げてみる。
雑談の中で自然に自己PRや価値観を織り込むことができれば、印象に残ります。
まとめ:雑談は「最後のテスト」
「最終面接が雑談だった」という体験談はよく耳にしますが、安心するのはまだ早いです。
企業にとって雑談は、学生が自然体の中でどうふるまうかを確認する“最後のテスト”。
和やかな雰囲気に飲まれて油断してしまうと、敬語の崩れや態度の軽さで評価を落とすこともあります。
逆に、丁寧に・誠実に・前向きに雑談を楽しむ姿勢を見せられれば、それは大きなプラス評価につながります。
最終面接を控えている方は、「雑談だからこそ見られている」という意識を忘れずに臨んでくださいね。
一緒に就活を乗り越えて、納得のいく内定をつかみましょう!
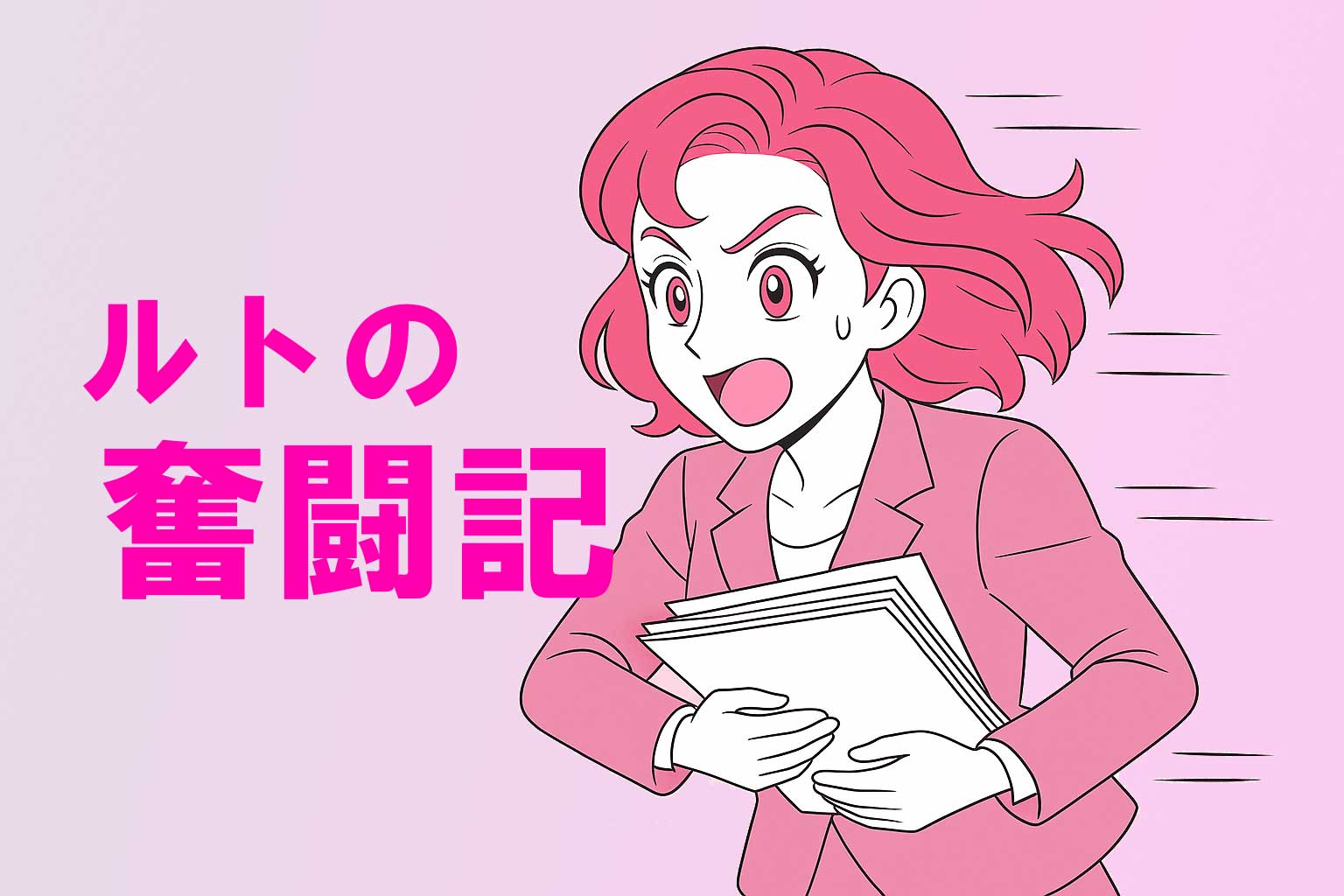


コメント