こんにちは、ルトです。
就活の面接を受けたことがある方なら、きっと一度はこんなシーンに出会ったことがあるのではないでしょうか。
「最後に、何か質問はありますか?」
いわゆる「逆質問」です。
就活サイトやハウツー本を見ると、よくこう書かれていますよね。
- 「逆質問をしないと落ちる」
- 「ここで差をつけるのが内定のカギ」
でも、採用担当としてたくさんの学生さんと向き合ってきた私から正直にお伝えすると―― そんなに気にしなくて大丈夫です!
もちろん、逆質問ができればプラスの印象を与えることもあります。
でも「逆質問をしなかった=落ちる」というシンプルな公式は存在しません。
むしろ、無理に質問をひねり出す方が、逆効果になることだってあるんです。
今日は、「逆質問って結局どうすればいいの?」と悩む学生さんに向けて、採用担当のリアルな本音をお話ししたいと思います。
逆質問は何のためにあるの?
まずは逆質問がなぜ存在するのか、企業側の視点を少しご紹介します。
1. 疑問を解消してもらうため
面接は企業から学生に質問を投げかける場であると同時に、学生にとっては企業を知る機会でもあります。
「入社してからこんなはずじゃなかった」と早期離職されてしまうのは、学生にとっても企業にとってもマイナスです。
だから最後に質問のチャンスを設けるのです。
2. 会話のキャッチボールを見るため
面接は単なる試験ではなく「対話の場」。
学生がどのように話を広げるか、相手の話をどう受け止めるかを知る機会でもあります。
3. 志望度を確認するため
「本当にうちの会社に興味を持っているのかな?」
その確認として逆質問を使う企業もあります。
ただしこれは絶対条件ではなく、むしろ「逆質問がなくても丁寧に受け答えしていたら十分好印象」というケースも多いです。
無理に逆質問すると逆効果?
ここでよくあるのが「何か聞かないと落ちるかも」と焦って、準備不足のまま質問してしまうパターンです。
例えば👇
- 「福利厚生についてもっと教えてください!」
- 「御社の強みはなんですか?」
これ、一見すると良さそうに思えるかもしれませんが、実際の面接では微妙です。
なぜなら すでに会社のHPや説明会で説明済みの内容 だから。
面接官によっては「調べてきてないのかな?」と感じてしまうこともあります。
逆質問がマイナス評価につながるとしたら、まさにこういうケースなんです。
「特にありません」は本当にNG?
多くの学生さんが不安に思うのが、「質問がないとマイナス評価なのでは?」ということ。
でも、私はそうは思いません。
実際に私が担当してきた面接でも、学生が「特にありません」と答えることはよくあります。
その際、ただ一言で終わってしまうと少し素っ気なく感じますが、工夫をすればむしろ好印象にもなるんです。
例えば👇
「会社説明会やOB訪問で十分に理解できましたので、現時点で追加で質問したいことはございません。」
これなら「ちゃんと調べてきている」「説明を聞いて納得している」と伝わります。
「採用担当がきちんと仕事してくれている」と思ってもらえると、私たちも悪い気はしません(笑)。
どうしても質問したいなら「人」に聞こう
逆質問をしたい、でもネタがない――そんなときは、面接官本人に関する質問がベストです。
例えば👇
- 「〇〇さんが入社を決めた理由は何でしたか?」
- 「働いてみて感じたギャップややりがいはありますか?」
- 「ご自身のキャリアの中で成長を感じた瞬間を教えてください」
こういう質問なら相手も答えやすいし、会話が少し雑談っぽく盛り上がることもあります。
「会社に興味がある」だけでなく「人に興味がある」と伝わるのも大きなポイントです。
学生さんに伝えたいこと
採用担当として感じるのは、逆質問を過剰に怖がっている学生さんがとても多いということです。
- 逆質問は必須ではない
- 「特にありません」は言い方を工夫すれば十分OK
- 質問するなら相手本人に関することがおすすめ
そして何より、面接は試験ではなく人と人との会話です。
「形式通りに逆質問しなきゃ」と思うより、自然にやり取りを楽しんでほしいな、といつも思っています。
まとめ
- 逆質問は義務ではない
- 無理に質問してマイナス印象になるより、自然体でOK
- 「特にありません」は丁寧に理由を添えれば問題なし
- どうしても聞きたいなら、面接官本人への質問が無難
- 面接は会話。自然さが一番大切
「逆質問しないと落ちる」と不安になる必要はありません。
大事なのは逆質問そのものよりも、全体を通してどんな人柄が伝わったか。
リラックスして臨むことが、結果的に一番の近道になるのではないでしょうか。
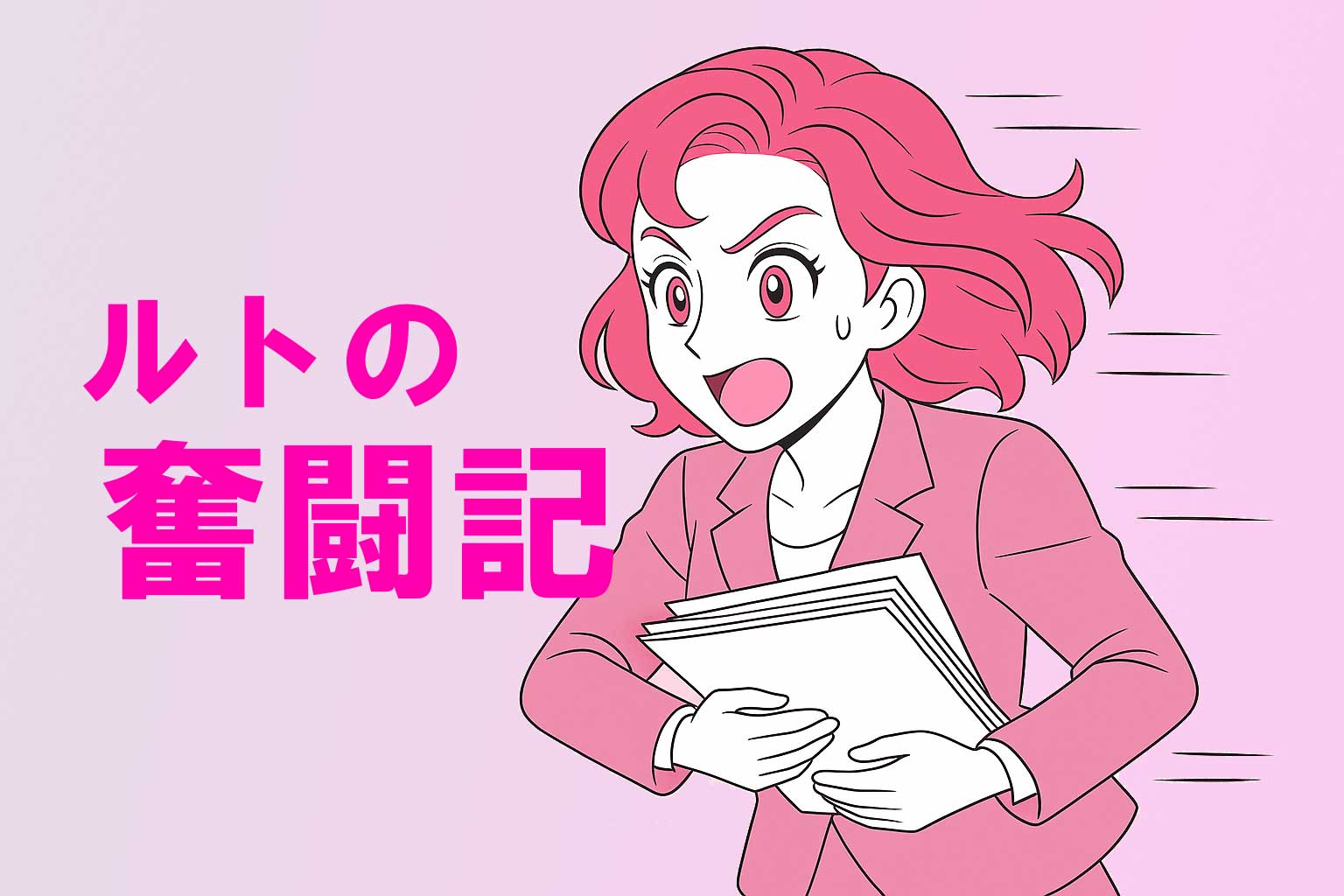

コメント